✔️本記事の内容
・バイクのすり抜けで捕まらないためにも気を付けたいポイント
・すり抜けをおすすめしない理由
本記事を書いている私はバイク歴10年のバイクオタクです。
今では基本すり抜けをしないような運転を心がけていますが、急いでいたりどうしてもすり抜けをしなければいけない場面では細心の注意を払って行っています。
普段からすり抜けをよくする方は是非読んでいってみてください。
バイクのすり抜けで違反として捕まるケースは珍しい
すり抜け行為は、よほど危険な場合でなければ実際に検挙されるケースはほぼないです。
すり抜けの検挙は全て対応していたら警察側もきりがないですし、タイミングによっては交通量などの関係で違反者を追う事すら難しいこともあります。
基本的には、止まっている車の間を安全な速度で白線・黄色線を跨いだりせずにすり抜けが出来ていればほぼ問題はありません。ここからは、実際の道交法においてどういった部分が違反に該当するのかを見てみましょう。
法的に規制されているバイクのすり抜けとは
道交法を確認してもすり抜けを直接的に規制しているルールはないですが、以下に該当する行為は検挙対象としてリスクが高いので、特に注意しましょう。
「追い越しは原則右側から」
(追越しの方法)第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
車両は、他の車両を追越そうとする場合において、前車が第25条第二項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
上記のとおりですが、原則追い越す際には前方車両の右側を走行するものとされています。
左側走行が認められているタイミングは前方車両が右折などを図っている際に右側・中央寄りを走行している時のみとされています。
「割り込みは禁止」
(割込み等の禁止)第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
すり抜けをした後に車両前方へ停車する行為は割り込みにあたり、違反行為とみなされます。
「交差点内への進入禁止」
(交差点等への進入禁止)第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。(罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)
「停止線を越えてはならない」
(信号の意味等)第二条 「赤色の灯火」
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと
上記をまとめると、要するにすり抜け後に停止線を越えようものなら
「交差点進入違反」と「信号無視違反」がセットで付いてきてしまうことになり兼ねないため注意が必要ということです。
すり抜け後に堂々と停止線を越えているライダーさんは割と多いですが、検挙されるリスクが高い行動だということを頭に入れておきましょう。
すり抜けをおすすめしない理由
個人的な経験から結論をお伝えするとすり抜けはおすすめしません。理由は以下の通りです。
①事故リスクが高まる
すり抜けをする時、したくなる時はほとんどの場合渋滞している時だと思います。渋滞しているときは死角がかなり増えますよね。
そして渋滞して交通の滞っている道路は、横断歩道の利用を横着した歩行者が割と小走りで渡ってきたり対向車の車がお店に入る為に右折をしてくることが多々あります。
教習所でも必ず習うケースですが、慣れてくるとみなさん忘れがちかもしれません。渋滞している道路を万が一すり抜けなくてはいけないときは、細心の「かもしれない運転」が必要になってきます。
【鉄則①】同じすり抜け組の後続車に煽られても、必ず徐行で走る
どうしてもすり抜けをしなくてはならない交通状況の際、あなたと同じすり抜け組の後続バイクからのプレッシャーを感じ、自然とスピードが増すこともあるでしょう。
すり抜け常習組は、普段からものすごいスピードですり抜けをしているので、煽られることもあるかもしれません。
ですが、すり抜けをする際は背後からのプレッシャーを気にせず、必ず低速走行しましょう。
【鉄則②】周りの車を信用しすぎない
渋滞中の車たちの動きは予測が難しいので、信用をしすぎない方が得策です。
例えば車のドライバーさんが「バイクを運転したことある方」であれば、すり抜けてくるバイクの存在に気をかけている可能性もありますが、世の中には、バイクに乗ったことがなくバイクの存在に恐ろしいほど注意を向けていない方がたくさん居ます。さらに渋滞中は、スマホを見ている方が多いです。
そのため発進時にふらつく車も多く、その間をすり抜けることはかなりリスキーです。そんなとき低速走行であれば、そんなイレギュラーな動きをしてきた車に対応しやすくなります。
②パンクリスクが高まる(路肩は異物がゴロゴロ)

道路というのは、水はけをよくするために路肩に向かってやや傾斜がかかっており、異物は大体路肩に転がっています。
そのため、左抜けによるすり抜けはパンクのリスクをかなり高めます。
工場地帯周辺などはより注意が必要
通勤先が工場地帯だったり、またはその辺りを通過する方や、ツーリングで工場の夜景を見に行くなんてこともあるかとは思いますが、工場地帯の路肩はまじで釘や鉄屑がよく落ちてます。
運搬のトラックから落ちたりして、一般の道よりも路肩は危険地帯と言えます。
あなたの近所にも思い当たるエリアがあればそこでは尚更左抜けによるすり抜けは控えたほうが良いでしょう。
一度のパンクでの出費はでかい
体験談ですが、私はスクーターのパンクで約3万、大型バイクのパンクにより約6万の出費が発生した経験を持っています。
ともに走行距離がある程度伸びていたためタイヤを前後交換したことと、バイク屋さんに現地まで引き取りに来てもらった引き取り代がかかったことなど、諸条件はありますが、時短の為にすり抜けをしまくった挙句の代償としてはかなり痛手でした。
まとめ
すり抜けが日常的・常習的になってしまっている方は、一度冷静になってそこまでしてすり抜けをする必要があるか見直してみるのもいいでしょう。
出発時刻を早めることでそこまで急いでバイクに乗る必要が無くなったり、どうしてもすり抜けるときは細心の注意を忘れないように心がけてみてください。
ただ、注意していても事故るときは事故ります。万が一に備えて、装備は万全にしておくべきでしょう。


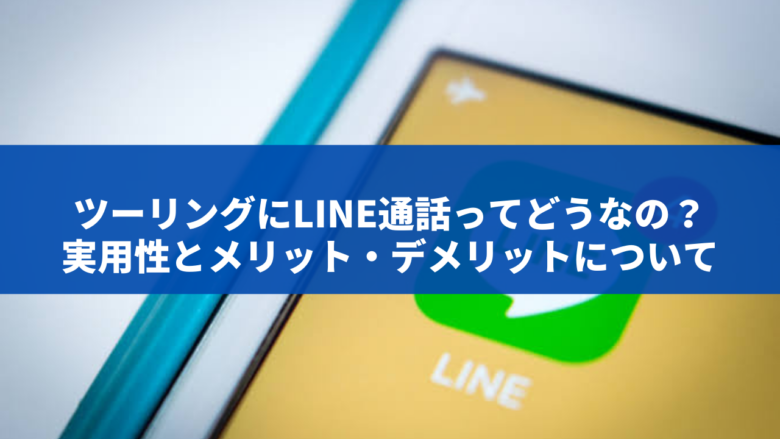
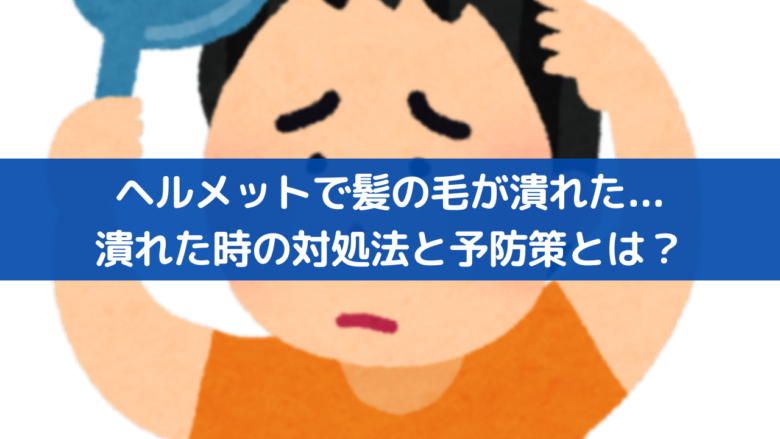
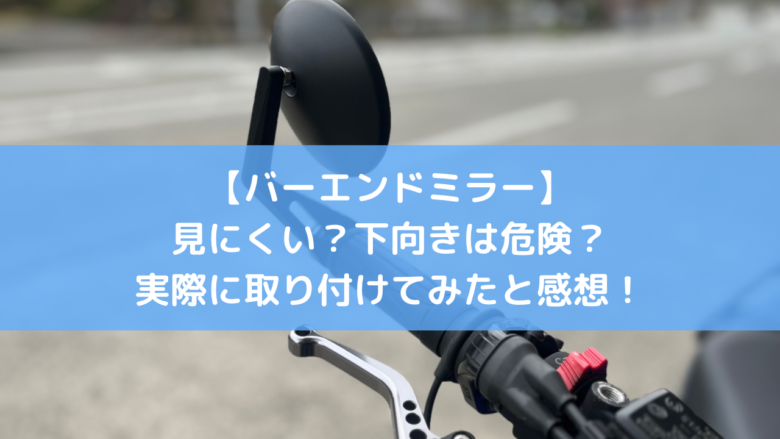

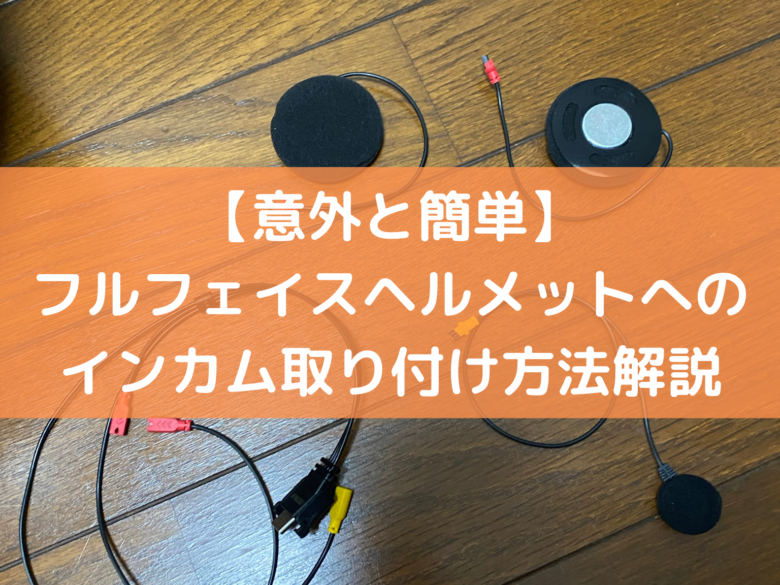




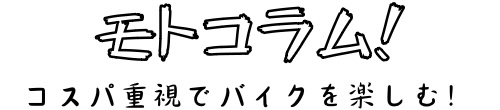
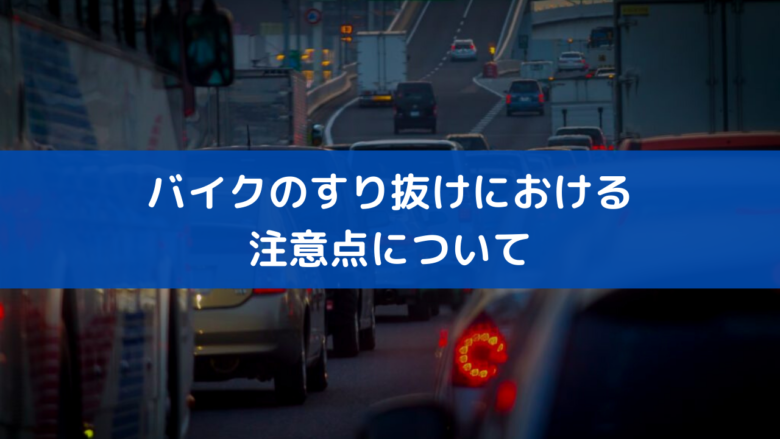
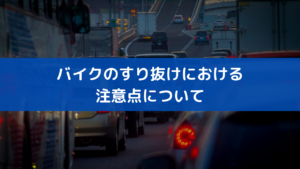
コメント
コメント一覧 (6件)
[…] […]
[…] 関連記事→すり抜けをよくする方に知っておいていただきたい事 […]
[…] こちらも合わせて!➡バイクのすり抜けはリスクがたくさんあります […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]